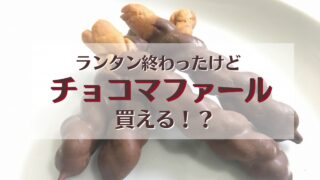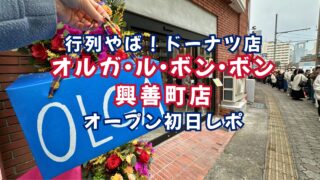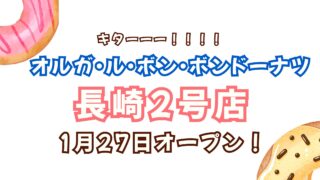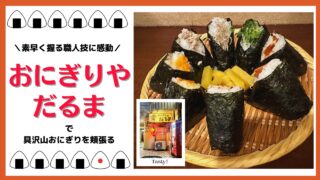はじめに
いよいよ10月、長崎くんちがやってきますね!
長崎の氏神・諏訪神社の秋季大祭「長崎くんち」は、毎年10月7日から3日間開催される伝統行事。
1634年に始まり390年以上続く奉納踊は国指定重要無形民俗文化財です。
踊町が7年に一度演し物を奉納し、龍踊や船回し、本踊など勇壮華麗な演目が披露されます。
「モッテコーイ」の声が響き渡り、街全体がお祭り一色に染まる長崎屈指の秋の祭りです。
今年の踊町について紹介します。
新橋町 本踊・阿蘭陀万歳(ほんおどり・おらんだまんざい)
新橋町は、かつて毛皮屋町と呼ばれていましたが、新しい橋の完成を機に改名。
現在は諏訪町に含まれますが、くんちでは新橋町として出演しています。
昭和26年に新橋町が初披露した「阿蘭陀万歳」は、南蛮衣装にシルクハットの万歳と、鼓を持つ才歳の掛け合いが魅力。
胡弓や木琴に合わせて踊り、町娘や唐子も登場する賑やかな演出で人気を集めています。
@shinbashimachi_nagasaki
諏訪町 龍踊(じゃおどり)
明治19年に初奉納。
昭和32年に青龍に加えて白龍、子龍を参加させ、昭和54年に白の子龍、昭和61年には孫龍も登場させ、大所帯へと発展しました。
基本構成の一つ「眠り」では、龍が玉探しで走り回って疲れ果て、寝ている様子を表し、玉の隠し場所が違うのが諏訪町独自の工夫です。
新大工町 詩舞・曳壇尻(しぶ・ひきだんじり)
新大工町は、明治34年に諏訪神社へ奉納した記録が残っています。
奉納は、袴姿の女性が詩吟に合わせて舞う「詩舞」と、囃子「式打」の後に豪快に引き回す「曳壇尻」の二部構成。
かつて多くの町で奉納された曳壇尻を、今も唯一伝承しているのが新大工町の大きな特色です。
@shindaikumachi_kunchi
榎津町 川船(かわふね)
榎津町は現在の万屋町と鍛冶屋町にあたります。
榎津町の川船は、囃方を乗せた船で子どもが船頭役を務め、投網の妙技を披露する演し物です。
網打ちや前後進、豪快な引き回しで川の激流に翻弄される様子を表現し、迫力満点。
最大の見どころは、直線的な動きから掛け声「サーヨーイヤサ」とともに踵を返すように一気に旋回する瞬間です。
@enokidumachi_kawafune_official
西古川町 櫓太鼓・本踊(やぐらだいこ・ほんおどり)
相撲興行の開閉場を知らせる小道具「櫓太鼓」と、本踊では、おめでたい「三番叟」が披露され、白いさらしが清々しく空を舞う姿が好評です。
今年は、元大相撲力士・旭道山和泰氏から借り受けた化粧まわしを用いて奉納します。
@nishifurukawamachi_kunchi
賑町 大漁万祝恵美須船(たいりょうまいわいえびすぶね)
「網上げ」と呼ばれる子どもたちによる網引きが見どころの一つ。
船頭役の子どもが実際に2kg級の生きた鯛を吊り上げる場面もあり、観客を沸かせます。
続いては大人衆が勇壮に引き回しを行い迫力満点。
船の指揮は大太鼓のみでとり、笛を使わない独自の構成が特徴です。
@nagasaki.nigiwaimachi
まとめ
以上、今年度の踊町の紹介でした。
今年も長崎の町を熱く彩る奉納踊を一緒に楽しみましょう!
・長崎くんち塾(2019) 『長崎遊学6 「もってこーい」長崎くんち入門百科』株式会社長崎文献社
・長崎伝統芸能振興会
・長崎市公式観光サイト travel nagasaki
・長崎新聞(2025年9月16日)「351年続く伝統の危機」元力士・旭道山さんの化粧まわし 西古川町に貸与 長崎くんち